自分はiPhoneユーザーなんだけど、AndroidアプリはJavaで書けるし、SDKも無料で手に入るので挑戦してる。(エミュレーターもついてるよ)
AndroidSDKダウンロードはこちらより
そんで、どうせならopengGL ESにも手を出そうかと。
でもopenGLについてもほとんど知らないので、初歩的なことからメモしてく予定。
まず、Androidに限らず、JavaでopenGLを扱う場合の注意点。メモリ管理の問題。
ご存知のように、Javaではガーベッジコレクタが勝手にアクセスの無いメモリを回収するので、メモリの開放とか考えずにコーディングできる。(組み込み系プログラマにJavaプログラマがバカにされちゃう理由でもあるね)
でも、この機能がopenGLでは邪魔になるようで。(openGL自体はCでできてる)
ということで、3Dオブジェクト用のメモリを確保するには、javaのガーベジコレクションの影響を避けるためにjava.nio.BufferクラスのByteBuffer型を使う必要があるらしい。
FloatBuffer型もあるけど、ByteBuffer型でないとメモリの並べ方を指定できないのでByteBuffer型を使う。
例えば、0x12345678をメモリに並べるには2つの方法があって、ビッグエンディアン(0x12, 0x34, 0x56, 0x78)とリトルエンディアン(0x78, 0x56, 0x34, 0x12)がある。
で、二つのどっちかは分からないけど、プログラムを動作させるハードウェア固有の並べ方でメモリを使う必要がある。
4つの頂点のバッファを確保する場合はこんな感じ(floatの4バイト×3Dベクトルだから3つ×頂点の数4つ)
ByteBuffer byteBuffer= ByteBuffer.allocateDirect(4 * 3 * 4);
動作させるハードウェア用の並び方に指定。
byteBuffer.order(ByteOrder.nativeOrder());
ByteBuffer型から、FloatBuffer型を作る
FloatBuffersquare = byteBuffer.asFloatBuffer();
後は、これに頂点の値を並べたfloat型の配列を突っ込めばOK。
javaでのopenGLの関数の基本的な呼び出し方法は普通のopenGLとほとんど共通みたいだ。
参考サイト
関連記事
Boost オープンソースライブラリ
Open3D:3Dデータ処理ライブラリ
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 口のバランス調整
日立のフルパララックス立体ディスプレイ
ZBrushで仮面ライダー3号を造る 仮面編 Dam Sta...
昔Mayaでモデリングしたモデルをリファインしてみようか
オープンソースの人体モデリングツール『MakeHuman』の...
ZBrushの練習 手のモデリング
Model View Controller
MythTV:Linuxでテレビの視聴・録画ができるオープン...
WinSCP
OpenCVの顔検出過程を可視化した動画
UnityでLight Shaftを表現する
OpenGVのライブラリ構成
DUSt3R:3Dコンピュータービジョンの基盤モデル
MPC社によるゴジラ(2014)のVFXブレイクダウン
Blendify:コンピュータービジョン向けBlenderラ...
MFnMeshクラスのsplit関数
Subsurface scatteringの動画
社団法人 映像情報メディア学会
オープンソースの物理ベースレンダラ『Mitsuba』をMay...
映画『ブレードランナー 2049』のVFX
MetaHumanの頭部をBlenderで編集できるアドオン
ハリウッド版「GAIKING」パイロット映像
iOSデバイスと接続して連携するガジェットの開発方法
CycleGAN:ドメイン関係を学習した画像変換
iPadをWindows PCのサブディスプレイにする無料ア...
Processing
WordPress on Google App Engine...
HTML5・WebGLベースのグラフィックスエンジン『Goo...
写真に3Dオブジェクトを違和感無く合成する『3DPhotoM...
ZBrush キャラクター&クリーチャー
3D復元技術の情報リンク集
HD画質の無駄遣い その2
Unreal Engine 5の情報が公開された!
SIGGRAPH ASIAのマスコット
Quartus II
Verilog HDL
OpenVDB:3Dボリュームデータ処理ライブラリ
胡蝶蘭の原種
甲虫の色とか
プログラミングスキルとは何か?

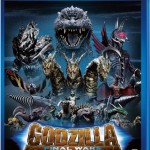
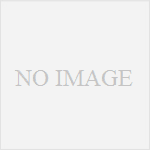
コメント