Unity関連のメモ。
UnityのScriptはMonoBehaviorクラスを継承して、オーバーライド関数を使って自前の機能を実装するわけだけど、それぞれの関数が呼ばれる順番を把握していないと、思わぬところで衝突してバグになる。
ちなみに、よく使う主なオーバーライド関数は以下。
Invoke() 設定したメソッドを、設定した秒数後に、一度だけ呼び出される。
Awake() スクリプトが読み込まれる時に、一度だけ呼び出される。
OnMouse◯◯()系 マウスが乗った時等に呼び出される。
OnTrigger◯◯()系 トリガー状態のオブジェクトとの衝突状態によって呼び出される。
OnCollision◯◯()系 オブジェクトの衝突状態によって呼び出される。
OnControllerColliderHit() キャラクターコントローラーの衝突の際に呼び出される。
OnEnable() オブジェクトが有効状態になった時に一度呼び出される。
OnDestroy() オブジェクトが破棄される直前に呼び出される。
OnApplicationQuit() アプリの終了直前に呼び出される。
OnGUI() GUIの描画やイベントを処理する関数。
http://qiita.com/hiroyuki_hon/items/0718a50e6569b6c5037a
そして、こちらはMonoBehaviorクラスのオーバーライド関数が呼び出される順番を図示したもの。(Unityの公式ドキュメントより)
以前は有志が図示したりしてた(Unity3D MonoBehaviour Lifecycle)けど、最近は公式でこんなにわかりやすく図を載せてるのね。
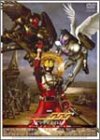

コメント