以前、C++でLocatorノードやShaderノードを作ったことはあったけど、C++はビルドの依存関係が結構面倒。もっと手軽に作りたくて、最近はPythonで書く方法を調べてる。
プラグイン開発の大枠はすでに理解してるんで、まあ、できるだろうと。書籍Maya Python 完全リファレンスも出てるし。
とりあえずロケーター作成の記事を見てみたら、やっぱり全体像はC++と同じみたい。
https://dftalk.jp/?p=3175
そんで、MayaのPython APIはバージョン1.0と2.0があることを知った。2.0はMaya 2012から使えるようになったらしい。
大きな違いはOpenMaya周りっぽい。→Maya Python API 2.0 Reference
今回はShapeノードを作ってみたいんだけど、公開されているサンプルコードはAPI 1.0で書かれていたので、それに倣って今回はAPI 1.0で作ることにする。
ShapeノードのPythonサンプルコードは以下2つ。(C++のリファレンスに混じってて見つけにくい)
さて、試しにこれらのサンプルをロードしてみると、一応Shapeノードとしてロードされるが、compute関数が空なので、ジオメトリはビューポート上に表示されるだけでレンダラには渡されない。つまり、Locatorと大差ないってこと。
全てのMayaノードはcompute関数を心臓部としていて、ここでoutputとなる情報を生成して出力のプラグに繋いでやる必要がある。Shaderの場合は、この出力がレンダラに渡す色になるわけ。
ということで、ちゃんとShapeノードとして機能させるには、ジオメトリのoutputアトリビュートを作ってcompute関数で値を生成してやる必要がある。
ここで参考になるのはC++の方のShapeノードのサンプル。apiMeshShape/~で始まるサンプルコードね。
- apiMeshShape/apiMeshShape.h
- apiMeshShape/apiMeshShape.cpp
- apiMeshShape/apiMeshShapeUI.h
- apiMeshShape/apiMeshShapeUI.cpp
- apiMeshShape/apiMeshData.h
- apiMeshShape/apiMeshData.cpp
- apiMeshShape/apiMeshGeom.h
- apiMeshShape/apiMeshGeom.cpp
- apiMeshShape/api_macros.h
- apiMeshShape/apiMeshCreator.h
- apiMeshShape/apiMeshCreator.cpp
- apiMeshShape/apiMeshGeometryOverride.h
- apiMeshShape/apiMeshGeometryOverride.cpp
- apiMeshShape/apiMeshIterator.h
- apiMeshShape/apiMeshIterator.cpp
- apiMeshShape/apiMeshSubSceneOverride.h
- apiMeshShape/apiMeshSubSceneOverride.cpp
結局C++を読む羽目になってるけど気にしない。
今日はここまで。
ところで、この手の書籍って何でノードよりもコマンドプラグインの解説が充実してるんだろう。

関連記事
NumSharp:C#で使えるNumPyライクな数値計算ライ...
C#で使える遺伝的アルゴリズムライブラリ『GeneticSh...
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 腕の作り込み
ジュラシック・パークの続編『ジュラシック・ワールド』
ゴジラ(2014)のメイキング
映画『シン・ウルトラマン』 メイキング記事まとめ
Unityで画面タッチ・ジェスチャ入力を扱う無料Asset『...
自前のShaderがおかしい件
ZBrushで仮面ライダー3号を造る 仮面編 失敗のリカバー
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 歯を配置
Iridescence:プロトタイピング向け軽量3D可視化ラ...
UnityでLight Shaftを表現する
オーバーロードとオーバーライド
adskShaderSDK
Texturing & Modeling A Pro...
ゴジラ三昧
顔追跡による擬似3D表示『Dynamic Perspecti...
WinSCP
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 頭頂部と首周りを...
Python拡張モジュールのWindows用インストーラー配...
Deep Learningとその他の機械学習手法の性能比較
OpenCVで動画の手ぶれ補正
プログラムによる景観の自動生成
Maya には3 種類のシェーダSDKがある?
openMVG:複数視点画像から3次元形状を復元するライブラ...
FreeMoCap Project:オープンソースのマーカー...
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 脚のトゲの作り直...
Cartographer:オープンソースのSLAMライブラリ
Faster R-CNN:ディープラーニングによる一般物体検...
網元AMIで作ったWordpressサイトのインスタンスをt...
Maya API Reference
ZBrush 2018での作業環境を整える
ManuelBastioniLAB:人体モデリングできるBl...
『手を動かしながら学ぶエンジニアのためのデータサイエンス』ハ...
ZBrushで仮面ライダー3号を造る 仮面編 ZRemesh...
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる モールドの彫り込...
OpenCV 3.3.0-RCでsfmモジュールをビルド
Webスクレイピングの勉強会に行ってきた
Unreal Engineの薄い本
OpenCVでPhotoshopのプラグイン開発
動的なメモリの扱い
ラクガキの立体化 目標設定
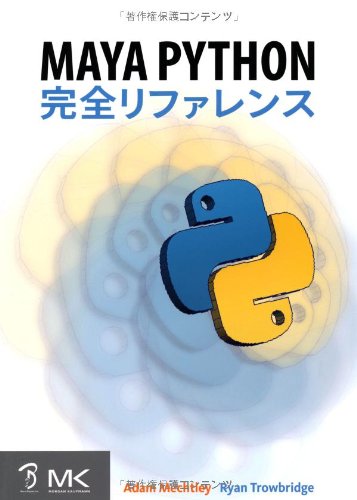

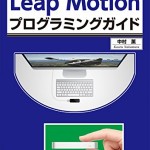
コメント