何となくモヤモヤしてたところで、こんな記事を見つけた。↓
ハッカースペースか、Makerスペースか、TechShopか、FabLabか?
最初に言っておこう。「ハッカースペース」と「Makerスペース」を区別している人は、実情に詳しい人の間でも、ほとんどいない。実を言うと、その人たちは、たいていハッカースペースに属している。私がこの2つの区別を付けようと考えた理由は、これらの名前の背景にあるコンセプトと表していることが、私の中で大きく離れていったからだ。
この記事によると、似ているようで指向が違うHackerスペースとMakerスペースというものがあるようだ。
2つのコンセプトをまとめると、
Hackerspace
プログラマー(ハッカー)の集まりから始まった。電子回路の設計製作など、興味の赴くままに物理的プロトタイプを行うようになり、「ハッカー」や「ハッキング」という言葉の定義が、物理的な物も対象にするようになった。ハードウェアの作り変え、電子部品の工作、プログラミングが主。既存のものを作りかえる(ハックする)場。
結果として、コミュニティが集産主義とつながる傾向にあり、意志決定に民主的方法をとるようになる。
Makerspace
2011年の初頭にDaleとMAKE Magazineが「デザインや工作のために誰もが利用できる場所」という意味でmakerspace.comという言葉を使い始めた。誰でも、いつでも、ほぼあらゆる材料を使って、既存のものを作り変えるのではなく、なんでも一から作れる場。
今流行っているMakers的なものはやっぱりMakerspace寄りな話みたい。自分なりに解釈すると、Makerspaceは既存のもののカスタマイズ(延長)ではなく、新しい用途・価値を生み出す場という意味だと思う。Hackerspaceはあくまで既存のものの延長、あるいは手を加える手段そのものを楽しむ場なんじゃないかな。
そして、アメリカにはMakerspaceを運営する団体が存在する。有名なのはTechShopとFabLab。
TechShopは、2006年にカリフォルニア州メンローパークに創設された営利目的のスペースチェーン。有料会員にハイエンドな工作機械を提供している。木工、機械工作、溶接、切断、CNC加工などの設備が揃っている。
FabLabは、2005年頃にMIT Media LabのCenter for Bits and Atoms所長とNeil Gershenfeldが立ち上げたスペースのネットワーク。元はMITで開かれていたHow to Make (Almost) Anythingという講義。FabLabの原則は、初心者でも工作機械の使い方や工学、デザインの簡単なレクチャーを受ければ、作りたいものが作れるようになるというもの。
FabLabには規格が定められている。

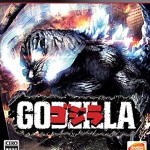
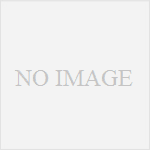
コメント