このブログ記事で興味を持ち、書籍「クラッシャー上司 平気で部下を追い詰める人たち」を読んだ↓
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2017/01/post-deef.html
平易な言葉で読みやすく、具体例をベースに200ページほどにまとまっていてすんなり読み終わった。

「クラッシャー上司」という言葉はてっきりネットスラングかと思っていたが、著者の松崎一葉氏が概念を世に広めるために意図して命名した呼称らしい。
それ以前は「潰し屋」と呼んでいた「部下を精神的に潰しながら、どんどん出世していく人」の精神構造を、著者が精神科産業医として診てきた例を基に紐解いていく。
悪意の無いクラッシャー精神
本書によると、「クラッシャー上司」の存在も昨今の「新型うつ」(著者は「未熟型うつ」という呼称を提唱している)の存在も、共通した精神構造に起因しているらしい。彼らは「未熟」である、と。「未熟」とか「共感性の欠落」といった点は自分にも思い当たる節があるのでちょっとドキッとする。
上司は悪意でクラッシャー化するわけではない。むしろその逆、組織のために善意で行動していたりする。そういう上司の下に「メランコリー親和型」と呼ばれる勤勉な性格の部下が付くと重症になりやすいんだとか。
クラッシャー被害者にできること
本書は「クラッシャー」の被害者がその状態から脱するための実用書を目指しており、最後の章は丸々「クラッシャー対策」に割かれている。
最近は、過労自殺や「チャレンジ」とか「不適切なプレッシャー」といった、昭和から続く滅私奉公の精神がそのままエスカレートしてしまった会社組織の歪みによる事件が相次いでいる。
著者によると、これらの事件も日本企業特有の時代背景が生んだクラッシャー的社会構造が見て取れるという。高度経済成長の名残を持つ日本企業には一定数のクラッシャーがいて当然で、それを前提に対策を知っておいた方が良い。
クラッシャー対策の中で、ストレスに対抗するためのリソース GRR(Generalized Resistance Resources)や、ストレス状況を乗り切る心の資質 SOC(Sense of Coherence)など、いくつか聞きなれない言葉も登場したけど、この辺を用意できていると潰れにくいのだとか。
あらゆるハラスメントに言えることだと思うけど、やってる側は無自覚なものなんだよね。
会社員になったばかりの頃は、上司や先輩は自分よりも経験があり、人間的にできていると思い込んでいたけど、別にそんなことはない。立派な人間だから出世したわけじゃないし、もしかしたら実力ですらなくて単なる年功序列かもしれない。
今という時代は、古き良き昭和の時代と比べて、色んな意味で余裕が無く、逃げ場が無い。上の世代が余裕のあった時代と同じ振る舞いをするだけで下は簡単に潰れてしまう。
古代の怪獣が突然現代で目覚めたみたいなシチュエーションだな。
関連記事
2024年の振り返り
2021年9月 振り返り
2019年12月 行動振り返り
『シン・ゴジラ』の感想 (ネタバレあり)
映画『大怪獣のあとしまつ』を観た (ネタバレ無し)
調べものは得意なのかもしれない
2018年 観に行った映画振り返り
2019年 観に行った映画振り返り
かっこいい大人にはなれなかったけど
書籍『ゼロから作るDeep Learning』で自分なりに学...
実写版『進撃の巨人』の後篇を観た(ネタバレあり)
感じたことを言語化する
2016年 観に行った映画振り返り
『きたぞ!われらのウルトラマン』を観てきた
『劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス』を観...
2022年5月 振り返り
注文してた本が届いた
書籍『コンテンツの秘密』読了
書籍『開田裕治 怪獣イラストテクニック』
自分を育てる技術
企画とエンジニア 時間感覚の違い
2018年10月~11月 振り返り
映画『オデッセイ』を観てきた
実写版『進撃の巨人』を観た (ネタバレあり)
Managing Software Requirements...
2019年9月 行動振り返り
ハードルの下げ方を学べば続けられる
映画『メッセージ』を観た
仮面ライダー4号
映画『THE FIRST SLAM DUNK』を観た
こんなところで身体を壊している場合じゃない
PS3用ソフト『ゴジラ-GODZILLA-』を買った
R-CNN (Regions with CNN featur...
S.H.MonsterArts 輝響曲 ゴジラ(1989)
自分の性質
2019年5月 行動振り返り
Googleが求める『スマート・クリエイティブ』と言われる人...
成果を待てない長学歴化の時代
動画配信ぐらい当たり前の時代
2020年3月 振り返り
S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 発売
2017年7月 振り返り
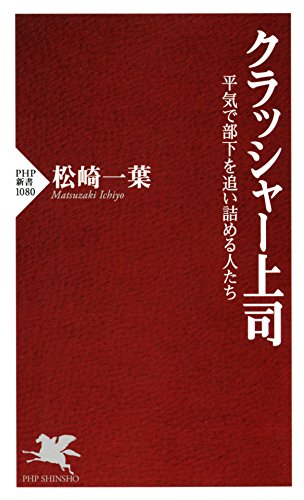


コメント