カーネギーメロン大学が開発している、顔画像から個人を識別するフレームワークOpenFaceと同じ名前で混乱しますが、
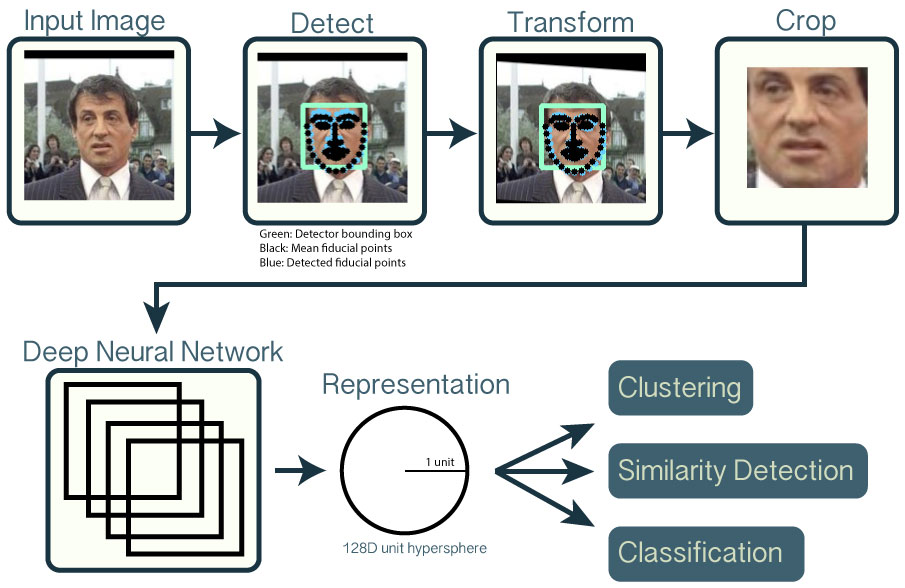
ケンブリッジ大学 Multicomp groupが開発しているOpenFaceという全く別のツールキットがあります。こちらは、顔検出、ランドマーク検出、頭の姿勢推定、表情変化の認識、視線推定などをリアルタイムに行うもの。
Copyright.txtによると、アカデミックまたは非商用に限り利用可能だそうです。商用利用は不可。
OpenFace: an open source facial behavior analysis toolkit
OpenFaceは、コンピュータビジョン・機械学習の研究者、情緒的コンピューティングのコミュニティ、顔の動作・表情の変化を用いたインタラクティブなアプリケーションの開発者を対象としたツールです。
OpenFaceは、顔のランドマーク検出、頭の姿勢推定、顔のAction Unitの認識、視線推定が可能な最初のツールキットです。OpenFaceのコアとなるコンピュータビジョンアルゴリズムは、上記のタスクすべてでstate-of-the-artな結果を示しています。
さらに、OpenFaceはリアルタイムに動作し、普通のウェブカメラで実行できます。特別なハードウェアは必要ありません。
Dockerfileもありますね。
公式Wikiはこちら↓
https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace/wiki
このツールキットの前身はCLM-framework(Cambridge face tracker)というフレームワークだったようです。↓
https://github.com/TadasBaltrusaitis/CLM-framework
YouTubeで公開されているデモ動画もCLM-framework時代のもの。
顔のAction Unitって概念、そういえばKinect SDKの顔認識機能でもあったな。FACS(Facial Action Coding System)の考えがベースだろうか。
関連記事
SSII 2014 デモンストレーションセッションのダイジェ...
コンピュータビジョンの技術マップ
Google App Engine上のWordPressでA...
UnrealCLR:Unreal Engineで.NET C...
UnityユーザーがUnreal Engineの使い方を学ぶ...
Point Cloud Utils:Pythonで3D点群・...
Pythonの自然言語処理ライブラリ『NLTK(Natura...
Unity MonoBehaviourクラスのオーバーライド...
TensorSpace.js:ニューラルネットワークの構造を...
書籍『3次元コンピュータビジョン計算ハンドブック』を購入
ミニ四駆を赤外線制御したりUnityと連携したり
BGSLibrary:OpenCVベースの背景差分ライブラリ
OpenCVでカメラ画像から自己位置認識 (Visual O...
CGのためのディープラーニング
ベイズ推定とグラフィカルモデル
Kinect for Windows v2の日本価格決定
python-twitterで自分のお気に入りを取得する
RefineNet (Multi-Path Refineme...
Webスクレイピングの勉強会に行ってきた
法線マップを用意してCanvas上でShadingするサンプ...
PGGAN:段階的に解像度を上げて学習を進めるGAN
UnityでLight Shaftを表現する
MFnDataとMFnAttribute
IronPythonを使ってUnity上でPythonのコー...
ブラウザ操作自動化ツール『Selenium』を試す
GeoGebra:無料で使える数学アプリ
ブログをGoogle App EngineからAmazon ...
『手を動かしながら学ぶエンジニアのためのデータサイエンス』ハ...
OpenMayaのPhongShaderクラス
iPhoneアプリ開発 Xcode 5のお作法
trimesh:PythonでポリゴンMeshを扱うライブラ...
Python2とPython3
Structure from Motion (多視点画像から...
JavaScriptとかWebGLとかCanvasとか
iOSで使えるJetpac社の物体認識SDK『DeepBel...
FCN (Fully Convolutional Netwo...
clearcoat Shader
ポリゴン用各種イテレータと関数セット
書籍『データビジュアライゼーションのデザインパターン20』読...
OpenMVS:Multi-View Stereoによる3次...
hloc:SuperGlueで精度を向上させたSfM・Vis...
OpenGVの用語
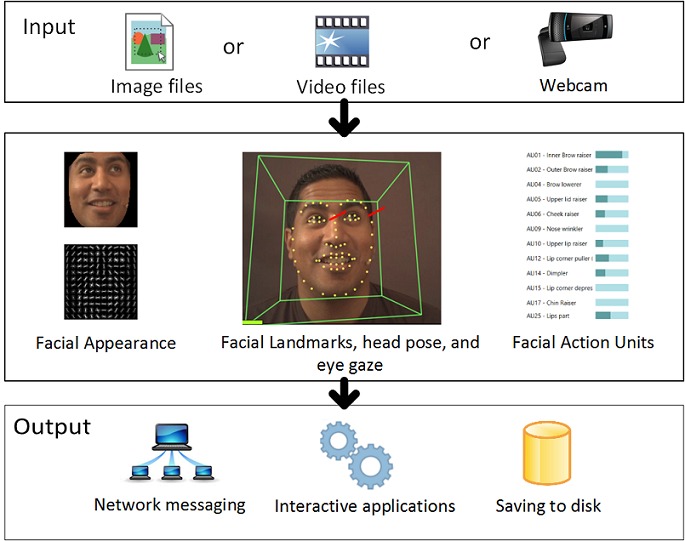

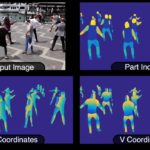
コメント