IoTブームだからなのか、IntelのEdisonみたいな小型のコンピュータが登場している。小さくても性能がそこそこのコンピュータが作れるようになったからIoTブームなのか?
その辺の関係は良くわからないけど、Raspberry Pi 2を買いました。(要するに単なるミーハーです)
最近おもちゃを買い過ぎですが、Edisonよりは安いです。
6倍越えのCPUパワーと2倍のメモリもお値段据え置き – 「Raspberry Pi 2」を試す

センサーと一緒にどこかに設置して、センシング情報を随時ネットワークに送るみたいなことをしてみたい。小さくてスペースを取らないし、消費電力も少ないはずだから、質素なセンサーと連携して常時稼働するセンシングサーバにはピッタリだ。(そういえば最近発表された新型Macbookもコアの部分は小さかったね。)
ということで調べる。
ここを見てOSのインストールまではできた。↓
はじめてのRaspberry Pi 2
ディスプレイとキーボード、マウスを繋いで作業するの面倒だから、早めにリモートでの操作に切り替える。↓
ラズベリーパイをリモート操作する
さて、Raspberry Pi 2のGPIOに、前に見つけた人感センサーのNapiOnを繋ごうと思うんだけど、GPIOの入出力はどうやってアクセスするんだろう。
と思って調べてみたら、GPIOをPythonから扱えるRPi.GPIOというPythonのライブラリがあるようだ。バージョン5.11以降では2でもちゃんと動くらしいぞ。↓
PyCharmを使ってRaspberry Pi2上で快適リモートGPIOプログラミング
デフォルトでPythonがインストールされているのね。
さあ、以降はこれ系を見てコーディングしながら試していくぞ。↓
Raspberry PIでLED点灯コントロール、Part2 Pythonでコントロールする
[Raspberry Pi]GPIOでLEDの点滅(Python)
RaspberryPiで人感センサーを作る
フランス語だけど、Raspberry PiからNapiOnを扱う記事見つけた。↓
Raspberry Pi et détecteur de présence infra-rouge
関連記事
Math.NET Numerics:Unityで使える数値計...
OpenMesh:オープンソースの3Dメッシュデータライブラ...
PythonのHTML・XMLパーサー『BeautifulS...
Konashiを買った
WordPressのテーマを自作する
Arduinoで作るダンボーみたいなロボット『ピッコロボ』
OpenCVの超解像(SuperResolution)モジュ...
このブログのデザインに飽きてきた
OpenCV 3.1のsfmモジュールを試す
UnityのGameObjectの向きをScriptで制御す...
Python拡張モジュールのWindows用インストーラー配...
ミニ四駆で電子工作
科学技術計算向けスクリプト言語『Julia』
openMVG:複数視点画像から3次元形状を復元するライブラ...
OpenCV 3.1とopencv_contribモジュール...
書籍『ゼロから作るDeep Learning』で自分なりに学...
iOSデバイスと接続して連携するガジェットの開発方法
Pylearn2:ディープラーニングに対応したPythonの...
WordPress on Windows Azure
HD画質の無駄遣い
adskShaderSDK
Python2とPython3
仮想関数
オープンソースの人体モデリングツール『MakeHuman』の...
Unity MonoBehaviourクラスのオーバーライド...
AfterEffectsプラグイン開発
海洋堂 20cmシリーズ『デスゴジ』 クリアーオレンジVer...
trimesh:PythonでポリゴンMeshを扱うライブラ...
Mean Stack開発の最初の一歩
3D復元技術の情報リンク集
CGレンダラ研究開発のためのフレームワーク『Lightmet...
機械学習で遊ぶ
手を動かしながら学ぶデータマイニング
COLMAP:オープンソースのSfM・MVSツール
AnacondaとTensorFlowをインストールしてVi...
WinSCP
MPFB2:Blenderの人体モデリングアドオン
Google Colaboratoryで遊ぶ準備
Google Chromecast
Iterator
OpenVDB:3Dボリュームデータ処理ライブラリ
2D→3D復元技術で使われる用語まとめ
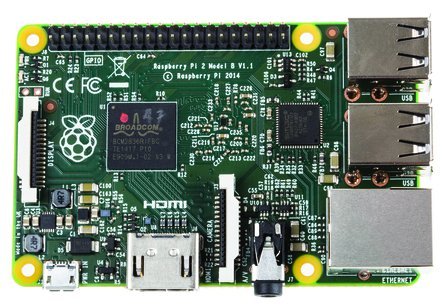
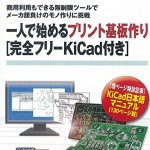
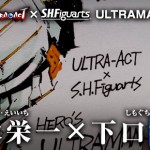
コメント