前の作業を見直してたら理解が進んだから、忘れる前にメモしておくよ。
PhongShaderのサンプルに載ってた関数についてのメモ。
MRenderUtil::raytrace(shaderからraytraceを扱うための関数)
static MStatus raytrace( const MFloatVector& rayOrigin, // in camera space const MFloatVector& rayDirection, const void* objectId, const void* raySampler, const short rayDepth, // storage for return value MFloatVector& resultColor, MFloatVector& resultTransparency, // true for reflected rays, false for refracted rays const bool isReflectedRays = true );
パラメータ:
[in] rayOrigin カメラ空間でのレイの始点座標
[in] rayDirection カメラ空間での飛ばすレイの方向
[in] objectID 現在のオブジェクトのID(未使用変数扱いされてたりもする?)
[in] raySampler レンダラから取得するレイトレーサーへのポインタ
[in] rayDepth レンダラから取得するこのレイの深さ(回数)
[in] resultColor 取得する色を格納する参照
[in] resultTransparency 取得する透明度を格納する参照
[in] isReflectedRays trueなら反射レイ(デフォルト)、falseなら屈折レイ
ということで、このサンプルサイトにある説明を訳してみた。
このユーティリティメソッドは、シェーダプラグインからレイトレースを行うための機能を提供します。
このメソッドは、レイの始点と方向を指定すると、単一のレイを飛ばし、交差点の色と透明度を返します。
シェーダープラグインでレイトレースを行うには以下の手順が必要です。:
レンダラにあるraySamplerを使います。これは’raySampler’ (rtr)という名前のinputアトリビュートを作成することで値を取得できます。
レンダラにあるrayDepthを使います。こちらは’rayDepth’ (rd)という名前のinputアトリビュートを作成することで値を取得できます。
Mayaソフトウェアレンダラ設定のrenderGlobal-> renderQuality->raytracingで”Enable Raytracing”のフラグをONにしておきます。
isReflectedRaysというBoolean変数は、飛ばすレイが反射レイか屈折レイかを示すものです。この変数はユーザーがrenderGlobal->renderQualityで設定した反射・屈折回数の制限をレイトレーサーに伝えるためのものです。
オブジェクトをレイトレースの対象とするには、”Visible In Reflections”または”Visible In Refraction”フラグがONに設定されている必要があります。
このメソッドは、Mayaソフトウェアレンダラでのみ動作します。
以上、Google翻訳頼りの翻訳でした。
関連記事
ZBrushで作った3Dモデルを立体視で確認できるVRアプリ...
BSDF: (Bidirectional scatterin...
OpenCVでPhotoshopのプラグイン開発
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる パーツ分割
openMVG:複数視点画像から3次元形状を復元するライブラ...
法線マップを用意してCanvas上でShadingするサンプ...
ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 頬の突起を作り始...
ZBrush キャラクター&クリーチャー
色んな三面図があるサイト
OpenAR:OpenCVベースのマーカーARライブラリ
Mayaのポリゴン分割ツールの進化
生物の骨格
参考になりそうなサイト
BlenderのGeometry Nodeで遊ぶ
3Dスキャンに基づくプロシージャルフェイシャルアニメーション
Mayaでリアルな布の質感を作るチュートリアル
プログラムによる景観の自動生成
ZBrushからBlenderへモデルをインポート
ZBrush 4R7
オープンソースの顔認識フレームワーク『OpenBR』
書籍『開田裕治 怪獣イラストテクニック』
プロシージャル手法に特化した本が出てるみたい(まだ買わないけ...
イタリアの自動車ブランドFiatとゴジラがコラボしたCMのメ...
Photo Bash:複数の写真を組み合わせて1枚のイラスト...
日立のフルパララックス立体ディスプレイ
CEDEC 3日目
ZBrush 2018へのアップグレード
Runway ML:クリエイターのための機械学習ツール
Javaで作られたオープンソースの3DCGレンダラ『Sunf...
フリーで使えるスカルプト系モデリングツール『Sculptri...
PureRef:リファレンス画像専用ビューア
Maya LTでFBIK(Full Body IK)
Unite 2014の動画
SIGGRAPH ASIA 2009で学生ボランティア募集し...
JavaによるCGプログラミング入門サイト (日本語)
画像生成AI Stable Diffusionで遊ぶ
書籍『The Art of Mystical Beasts』...
TeleSculptor:空撮動画からPhotogramme...
スクラッチで既存のキャラクターを立体化したい
実写と実写の合成時の色の馴染ませテクニック
Composition Rendering:Blenderに...
書籍『ROSプログラミング』


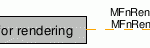
コメント